このブログを訪問してくださって、ありがとうございます。
シニアのあっこさんと申します。シニアです。私は50代後半になって、社会福祉の「しゃ」の字も知らずに通信教育で社会福祉士の資格を取ることにしました。資格取得できなくても、勉強の一つとして学ぼうと思ったのです。
この年ですから、通信教育。経験も全くないので、実習は必須でした。
でも、実習は免除になる方もいらっしゃいます。
今回は、その実習免除の条件と、実習先の選び方、そして私の場合の個人的な実習の様子をお伝えしたいと思います。
是非、ご一読を~!
実習の概要
23日以上かつ180時間以上がルールですが、養成施設ごとで2回に分けて実施するところもあります。2回に分ける場合は1施設での実習時間を120時間以上かつ15日以上、20日以内、もう一つの施設での実習を60時間以上かつ8日以上10日間以内で行うよう定められています。養成施設にそれぞれ確認される方がいいです。
2024年から実習時間が240時間に!
2024年度から、180時間の実習が240時間になります。実習を予定されている方は、早めに実習科目を履修されることをお勧めします。
以下は厚労省のホームページから。社会福祉養成課程における教育内容の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/content/000523365.pdf
実習の免除の条件
実習は必ずしも全員が必要ではありません。厚労省が定める相談援助の実務経験が1年以上ある方は実習免除となります。
介護福祉士または精神保健福祉士の国家資格を持つ人については60時間を上限として実習が一部免除になります。
実習については実習費用と実習委託費がかかります。養成施設の学費に記載がない場合もありますので、入学を検討される前に学費の内訳を確認しておきましょう。
実習免除となる施設、職種
実務経験があると、実習免除がありますが、具体的な実務経験の施設は社会福祉振興・試験センターのホームページに示されています。
福祉に関する相談援助の業務以外のお仕事を兼務されている方は、その兼務している事実が辞令によって明確であり、主たる業務が相談援助であることが必要となります。

このホームページに記載にある実務経験があると実習免除になることがあります。
実習先の選び方
様々な分野で実習ができますが、それぞれの養成施設が提携している実習先があります。その中から、ご自分に合った実習先を選ぶことになります。
社会福祉を全く知らない方は、どの機関がどのような働きをしているのか、全くわからないかもしれません。
私自身、なんとなく響きがいいかなと思って希望していたところは、社会福祉協議会。
でも、ここは比較的希望者が多く競争率も高く、私は実習先に選ぶことはできませんでした。
そこで、今一度考えていただきたいことは、
「なぜ、この資格を取りたいと思ったか」
ということです。この資格に興味を持たれたというこては、誰かの役に立ちたい、という思いがあったはずです。それは、高齢者だったり、障碍者だったり、子供たちだったり。その人たちの役にたちたいと思った分野を選ばれればよいかと思います。
私は、そもそも子供や障碍者の分野に興味があったので、指導の先生にはその旨をお伝えして、就労継続支援B型と呼ばれる作業所に実習に行くことになりました。
一つお伝えしておきたいことは、作業所や高齢者の施設などでは、どうしても実習というと、面談や機関との連携というよりは、むしろ利用者の方たちと一緒に作業をしたり、介護などのお手伝いを通して、利用者の方たちとコミュニケーションを取る、という実習になってしまいます。この実習になってしまうと、体力的には少し辛いものがあるので、体力に自信が無い方は、そこは避けた方がいいかもしれません。
いずれにしろ、どのような実習にしろ、そこから何かを学び取る、という姿勢が必要になってきます。
実習先で何も教えてもらえなかったと思われる方もいらっしゃるかもしれません。ですが、利用者さんと数週間一緒に過ごすことによって、何かの発見はあると思います。そこから、どう学び取るかは、指導もしてもらえますし、自分で「記録」をつけることで自分で社会福祉の力がついていきます。
どの実習先になっても、何かしらの学びはあると思いますので、是非頑張っていただきたいところです。
実習は結構大変 私の場合
私の実習先は、通称就労継続B型と呼ばれる作業所でした。知的障碍者が通ってきている作業所で、おおよそ20名ほどの方が利用されていました。スタッフの方は5名。
就労継続支援B型とは?以下も、厚労省のホームページから
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000571840.pdf
作業内容は、菓子箱の組み立てや、子供用のお菓子を袋に詰めたり、あられを作ったり。その販売を市役所でやったり。
一年目は90時間。二年目も90時間でした。一日7時間だとすると、一年目に13日間実習することになります。その間、土日、祝日はお休みになるところが多いので、実質2週間半を二回やることになりました。
一年目の実習
一年目はほぼ全部の時間、利用者の方と一緒に作業をしました。ラインのように並んで、その中に入って組み立て作業を行いました。次々と流れてくる部品を組み立てていくのはなかなかきつく、一日が終わるとぐったりしました。お昼休みは利用者の方たちと一緒に給食を食べました。給食の後も一緒に過ごしました。利用者の方が帰宅されると、その後で指導に当たっていただける所長さんとお話をする機会もありました。実際に私が帰宅できるのは、夜の7時から8時ごろ。それからその日一日の記録をつけます。記録は、手書きで気を付けるべきところがたくさんあります。書き方も独特の決まりがあります。
二年目の実習
二年目になると、他の関係機関との打ち合わせ等に連れて行っていただけるかと思いましたが、残念ながらそれは、ありませんでした。ただ、一人の利用者さんと面談して、時間内に、聞き取りを完了させる、緊張させないようにする、などを気を付けながら面談することができました。簡単そうに見えて、実は難しいことだと実感できました。
実習記録のつけ方と注意点
養成施設のスクーリングで、実習についての講義もありましたが、記録の書き方もしっかり時間を取って教えて頂きました。皆さんも、「記録」について、学ばれると思います。
私が今でも気を付けていることは、
客観的データと主観的データを別々に記載すること
個人名は、個人が特定されないように、必ずアルファベットか、本人、保護者、姉、祖母などという表現にすること
直接用紙にボールペン(消えないもの)で書いたので、書き間違いがあったら必ず訂正印を押してから書き直すことが必要
当時、帰宅して家族の食事を用意し、記録をつけて就寝につくのは、夜中の12時を過ぎることもよくありました。
実習のまとめ
当時はきつい、と感じたものでしたが、1年のうち2週間と少しです。さらに、中々体験できることではなく、新鮮なことはたくさんあります。
今まで思っていなかった、障害を持つ方たちは私たちと全く同じように感じ、同じように才能も持っている、困った行動は、その人が困っている、ということが実感できたことは、大きかったです。この実習が過ぎたあとは、街中で他の方がよけてしまうような、障害を持った方が通っても、全く気にならなくなりました。むしろ、何か困っていたら助けてあげられるかも、という意識に変わったのは、とても大きいと思います。
他の学生の中には、実習生向けのプログラムがとてもしっかりしており、きちんとした講義を企画され、2週間でしっかり学習できるように計画されていた施設もあったそうです。でも、学べることはそれぞれあります。是非、実習に臆することなく、チャレンジして楽しんでいただけることが最大のポイントかなと思います。
頑張ってください。
NEXT


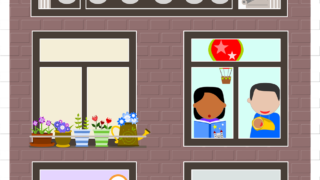




コメント